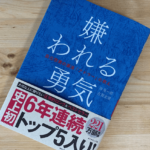世の中が便利になりすぎて何でも簡単に手に入るようになった。
コンビニにいけば、食料から日用品、宅配やATMなどのサービスも充実している。
今からひと昔前では考えられないほど便利になった。
便利になったのは、モノやサービスだけではない。
一番大きいのはスマホの普及でインターネットでどんな情報も簡単に手に入るようになったことではないだろうか。
その恩恵はたくさんあるが、最近ビックリしたのが
Youtubeを見ていると、読書など時間をかけないと手にはいらない知識が
「10分で要約!」
といったキャッチフレーズでわかりやすく解説されていたりする。
「いや~、ほんとすごい」
普通に読めば早くて2時間、ゆっくり読めば5時間はかかるだろう本を、わずか10分。
そんなばかなと思いながら見てみると、これがなかなか要点をまとめられていて面白い。
しかし、ここで1つの疑問がわいた。
「簡単に身についたものは、簡単に忘れるのではないだろうか?」
見ているときは関心し、ためになったと喜んでも、果たして明日以降も覚えているだろうか。
エビングハウスの忘却曲線によると、1日たつと人は覚えた知識の約70%を忘れるのだそう。
人は寝るという行為を通じて脳内で記憶を整理している。
つまり、必要な記憶と不要な記憶の仕分けをしているのだ。
記憶のメカニズムとして、強い感情を伴うことも大きく影響する。
ショックな出来事は10年以上たっても鮮明に覚えていたりする、といったことだ。
それなら、その10分に要約された本は1か月後、1年後、どれだけ記憶として残るのだろうか。
おそらく、1%も残らないのではないだろうか。
では、たとえ10分であろうと、その視聴した時間は無駄になるのでは?
と次に考えが浮かぶ。
しかし、それはおそらく人によって違うだろう。
無駄になる人もいればその得た知識を活かしている人もいる。
その違いは、本の情報をとるときの「目的意識」の差にあると思う。
そもそも、本をなぜ読むのか?
それは、日常生活や仕事でその知識を活かすためではないだろうか?
本のタイトルを見て、
「この本を読めば、自分もこういうことができる人間になる」
という期待をもっているはずで、だから手にとってみる。
つまり、本を読む本質は、得た知識を活用できるレベルに自分の血肉とすることだ。
それには、普段から自分に対して問題意識を明確に持っているかが重要となる。
問題意識が明確だと、
「これを解決したい!!」
と、強い欲求がうまれる。
解決したい問題があり、それを自分の力で解決できないから、本から教わる。
そう考えると、10分の要約もあながち、無意味なことはない。
なぜなら、10分の内容のなかに自分の問題を解決できるヒントがあるなら、
それを人は忘れないように繰り返し覚えようとするからである。
10分の要約の視聴が無駄にならないためのポイントは、本を読むまえに
「自分の問題点は何か?どうやったら解決できるか?」
と思考をしっかりしておくことでだ。
「思考」
これだけは、いくら世の中が便利になろうとも、コンビニ感覚では手に入れることのできないものである。